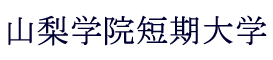人間と教育
学びの本質を考える—人間と教育の多様な関係
初田宏樹
2単位
保育科
| 履修系統図番号 | 4NPC-0304 |
|---|---|
| 科目区分 | 一般基礎教育科目 |
| 必修、選択の別 | 選択 |
| 授業形態 | 講義 |
| 到達目標 | 教育を「学校教育」だけでなく「社会・家庭・個人の成長」という視点から多角的に考え、以下の能力を育成することを目標とする。
・教育の本質を理解し、多角的な視点を持つ 教育の役割と変化を学び、歴史・社会・科学の観点から考えられるようになる。 未来の教育の可能性について、自らの意見を持つ。 ・学習意欲やモチベーションの向上につながる要因を理解する 「やる気」「モチベーション」に関する理論を学び、自身の学びや指導に活かす。 教育と人間関係の関係を考察し、実践的なコミュニケーション力を養う。 ・教えること・学ぶことの本質を理解し、人間関係の構築における教育の重要性を知る。 共同作業を通じて、協調性や問題解決能力を育てる。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 本授業では、「教育とは何か?」を幅広い視点から考え、学び・人間関係・モチベーション・社会との関わり など、多角的に教育を捉える力を養う。ディスカッションや活動を取り入れ、受講者自身が「教育の本質」について深く考え、主体的に学ぶ姿勢を育むことを目的とする。 | ||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | オリエンテーション –「教育」とは何か?
目的: 「教育」の概念を整理し、学問としての教育学を考える 内容: 教育の定義(学校教育 vs. 社会教育 vs. 生涯学習) 「自分にとっての教育とは?」を考える 活動: 「私に影響を与えた教育体験」 |
第1回:オリエンテーション –「教育」とは何か?
事前学習: 「教育とは何か?」を考え、身近な教育体験(学校・家庭・社会での学び)を振り返る。 事後学習: 「自分にとっての教育とは?」を300字でまとめる。 教育の定義や役割について意見を交換し、次回の授業で共有。 |
| 2回 | これからの教育 – 社会の変化と教育の未来
目的: 教育の役割が時代とともにどう変化しているのかを理解する 内容: AI・ICT・オンライン教育の発展 未来の学校・教師の役割 活動: 「未来の学校はどうなる?」ディスカッション(グループで未来の教育制度を考え、発表) |
第2回:これからの教育 – 社会の変化と教育の未来
事前学習: ICT・AIが教育に与える影響に関する記事を読んでおく。 フィンランドやシンガポールなどの教育先進国の事例を調べる。 事後学習: 「10年後の教育はどう変わるか?」をテーマに、未来の学校を想像してまとめる。 |
| 3回 | やる気・モチベーション – どうすれば人は学び続けられるか?
目的: モチベーション理論を学び、教育や自己成長に活かす 内容: 内発的動機づけ・外発的動機づけ(自己決定理論) 「楽しい学び」と「強制される学び」の違い 活動: 「自分のモチベーション曲線」作成(自分が学びに対してやる気を感じた瞬間を振り返る) |
第3回:やる気・モチベーション – どうすれば人は学び続けられるか?
事前学習: 「内発的動機づけ」「外発的動機づけ」に関する資料を読む。 自分が学びに熱中した経験を振り返る。 事後学習: 友人や家族に「何をしているときに一番やる気が出るか?」をインタビューし、データをまとめる。 |
| 4回 | 人間関係と教育 – コミュニケーションの重要性
目的: 人間関係の中で学ぶことの重要性を理解する 内容: ピア・ラーニング(協同学習)とは 先生・友人・家族との関係が学びに与える影響 活動: 「理想の先生とは?」ワークショップ(グループで理想の教師像を考え、発表) |
第4回:人間関係と教育 – コミュニケーションの重要性
事前学習: 「ピア・ラーニング」「協同学習」について調べる。 自分が影響を受けた先生・友人・家族との関係を振り返る。 事後学習: 「良い人間関係を築くために大切なこと」をグループでまとめる。 |
| 5回 | 教えるということ –「教える」は誰のため?
目的: 教える行為の本質を考える 内容: 「教える」と「学ぶ」は表裏一体 説明することの難しさ 活動: 「相手に伝えるワーク」(身近なものを1分で説明し、相手がどれだけ理解できるか試す) |
第5回:教えるということ –「教える」は誰のため?
事前学習: 「ティーチング」と「コーチング」の違いを調べる。 人に何かを教えた経験を思い出し、難しかったことを書き出す。 事後学習: 「学んだことを教えることで、自分はどう成長するか?」を300字でまとめる。 |
| 6回 | 金銭教育 – お金の使い方をどう学ぶか?
目的: 金銭教育の重要性と教育との関連を学ぶ 内容: ファイナンシャルリテラシーとは? 日本と海外の金銭教育の違い 活動: 「10万円を使って社会貢献」ワーク(架空の10万円をどう使うかを考え、教育的視点で発表) |
第6回:金銭教育 – お金の使い方をどう学ぶか?
事前学習: 日本の金銭教育の現状と、海外の事例(アメリカ・フィンランドなど)を調べる。 事後学習: 「教育現場での金銭教育の在り方」を提案し、具体的な活動プランを作成。 |
| 7回 | ゲームと教育 – ゲームは悪か、教育ツールか?
目的: ゲームが教育に与える影響を考える 内容: ゲームが学習に与える影響(プラス・マイナス) ゲーミフィケーションとは? 活動: 「教育ゲームを考える」(学びにつながるゲームのアイデアを出す) |
第7回:ゲームと教育 – ゲームは悪か、教育ツールか?
事前学習: ゲーミフィケーションの成功事例を調べる。 自分のゲーム経験(ポジティブ・ネガティブ両方)を書き出す。 事後学習: 「ゲームを活用した学びのアイデア」を提案し、次回ディスカッション。 |
| 8回 | ICTと教育 – 教育のデジタル化は何を変えるのか?
目的: ICT教育のメリット・デメリットを理解する 内容: オンライン教育の可能性と課題 学習データの活用と個別最適化学習 活動: 「ICT授業 vs. アナログ授業」ディベート |
第8回:ICTと教育 – 教育のデジタル化は何を変えるのか?
事前学習: オンライン授業・ハイブリッド学習のメリット・デメリットを考える。 事後学習: 「ICTを活用した授業設計」を考え、簡単な指導案を作成。 |
| 9回 | フィンランド vs. 日本の教育 – 比較して考える
目的: 教育システムの違いを知り、教育の多様性を理解する 内容: フィンランド教育の特徴(自由・探究・PISAトップ) 日本の教育との違い 活動: 「もしフィンランドの教育を日本に導入するなら?」を考える |
第9回:フィンランド vs. 日本の教育 – 比較して考える
事前学習: フィンランド教育の特徴を調べる(PISA、自由な学習スタイルなど)。 事後学習: 「日本の教育に取り入れられる改革案」を提案し、レポートにまとめる。 |
| 10回 | 自己肯定感を育む教育とは?
目的: 自己肯定感の重要性を理解し、教育との関係を学ぶ 内容: 日本の子どもの自己肯定感の低さの問題 ほめ方・叱り方の心理学 活動: 「ほめる・叱るロールプレイング」 |
第10回:自己肯定感を育む教育とは?
事前学習: 「ほめ方・叱り方の違い」を心理学の視点で調べる。 事後学習: 「自分が今まで受けたほめ方・叱り方」の事例を分析し、改善案を考える。 |
| 11回 | 「知識」だけではダメ?21世紀に求められる力とは
目的: 未来に必要な教育の在り方を考える 内容: 知識 vs. 思考力 vs. 創造力 PBL(プロジェクト型学習)の可能性 活動: 「21世紀型の授業をデザイン」 |
第11回:「知識」だけではダメ?21世紀に求められる力とは
事前学習: 21世紀型スキル(クリティカルシンキング・創造性)について調べる。 事後学習: 「これからの時代に必要な教育」をテーマに、提案をまとめる。 |
| 12回 | 教育と格差 – 学ぶ機会の不平等
目的: 教育格差の現状と解決策を考える 内容: 経済格差と学力格差 無償教育・奨学金のあり方 活動: 「教育格差をなくす方法」ブレインストーミング |
第12回:教育と格差 – 学ぶ機会の不平等
事前学習: 教育格差の実態(家庭の経済格差が学力に与える影響など)を調べる。 事後学習: 「教育格差をなくすために自分ができること」を考え、グループで議論。 |
| 13回 | 多様性とインクルーシブ教育
目的: 障害・国籍・性別の壁を越えた教育を考える 内容: インクルーシブ教育の理念 世界の多文化教育の事例 活動: 「多様性を尊重する学校づくり」ワークショップ |
第13回:多様性とインクルーシブ教育
事前学習: インクルーシブ教育の定義と具体例を調べる。 事後学習: 「多様性を尊重する授業デザイン」を作成し、発表。 |
| 14回 | 未来の学校をデザインする
目的: これまでの学びを活かし、新しい教育の形を考える 活動: 「10年後の理想の学校をデザイン」プレゼン大会 |
第14回:未来の学校をデザインする
事前学習: 世界の「未来の学校」プロジェクトを調べる(イノベーティブスクールなど)。 事後学習: 自分が理想とする学校の概要をスライドにまとめる。 |
| 15回 | 定期試験 | |
| 16回 | 定期試験の解説
授業評価の実施と総評 本講義のまとめ「私にとっての教育とは?」 |
事前学習:
これまでの授業内容を振り返り、自分が特に印象に残ったことを整理する。 事後学習: 「私にとっての教育とは?」を1000字程度でまとめる。 |
| 成績評価の方法・基準 | 定期試験の解説と総評
授業評価の実施 筆記試験60%・レポート40% |
|---|---|
| 教科書・参考書 | 特になし |
| 履修条件 | なし |