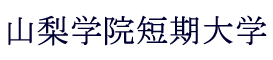子どもの理解と援助
雨宮基博・清水一毅
1単位
保育科
| 履修系統図番号 | 9C-2012 |
|---|---|
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 必修、選択の別 | 選択 教職必修(幼) 保育士必修 |
| 授業形態 | 演習 |
| 到達目標 | 1.子ども理解についての知識を身につけ、考え方や基本的態度を理解する。
2.子ども理解の方法を具体的に理解し、子どもを科学的な方法により観察ができる。 3.観察と理論に基づき、子どもの心情、子ども間の関係、保護者の心情などを理解し、適切な対応を説明することができる。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 子どもとの信頼関係を築き、一人一人に応じた指導をすること、また、発達に必要な経験を幼児自らが獲得できるように援助していくことの基本は、子ども一人一人の内面の理解(子ども理解)である。この科目では、「発達心理学」等で学んだ基本的な対象理解、また、学外実習で子どもと接した経験を踏まえ、さらに子ども理解と方法を解説し、考察する。
適宜グループディスカッションを実施する。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | 子ども理解の意義・原理とその視点 | 保育における子ども理解の意義、子どもとの関わりにおける基本的態度
事前学習:シラバスの確認(30分) 事後学習:子ども理解の意義・子どもと関わる基本的態度についてまとめる。(60分) |
| 2回 | 子どもの発達と保育者の関わり | 保育の人的環境としての保育者の役割、子どもの発達との関係について学ぶ。
事前学習:自身の実習記録から子どもの発達を支える保育者の役割について考察する。(45分) 事後学習:子どもの発達おける保育者の役割についてまとめる。(45分) |
| 3回 | 子ども理解の方法 | 子どもを理解する方法として、観察・記録、省察・評価、対話を通した子ども理解について学ぶ。
事前学習:自身の実習記録から子どもを理解する方法について考察する。(45分) 事後学習:子どもを理解する方法についてまとめる。(45分) |
| 4回 | 遊びと通じた学び | 子どもの遊びを通じた学び、それを支える保育者の関わりについて学ぶ。
事前学習:自身の実習記録から遊びを通じた学びを支える保育者の関わりについて考察する。(45分) 事後学習:遊びを通じた学びを支える保育者の関わりについてまとめる。(45分) |
| 5回 | 個と集団の関係 | 集団における個・集団への適応
事前学習:集団と個の関係について文献等調査(45分) 事後学習:事後課題に取り組む。授業内容についてノートにまとめてみる(45分) |
| 6回 | 子どものつまづきの理解とその援助 | ICIDHとICF
事前学習:ICIDHとICFについて文献等調査(45分) 事後学習:事後課題に取り組む。授業内容についてノートにまとめてみる(45分) |
| 7回 | 保護者の心情と保護者への対応の基本 | 環境調整
事前学習:環境調整について文献等調査(45分) 事後学習:事後課題に取り組む。授業内容についてノートにまとめてみる(45分) |
| 8回 | 総括講義 | 保護者対応・保育記録
事前学習:現場における保護者支援について文献等調査(45分) 事後学習:事後課題に取り組む。5〜8回の内容に関するレポート課題の作成(240分) |
| 成績評価の方法・基準 | 各担当教員によって50%ずつ評価を行う。
雨宮:期末レポート60% 提出物40% 清水:期末レポート60% 授業内の課題提出40% |
|---|---|
| 教科書・参考書 | <参考文献>
・清水益治・無藤隆(編著) (2021) 「新保育ライブラリ 子どもを知る 子どもの理解と援助」 北大路書房 (¥1800) |
| 履修条件 | なし |