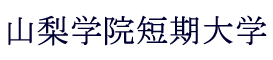卒業演習Ⅰ
演習担当教員
1単位
保育科
| 履修系統図番号 | 12C-1005 |
|---|---|
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 必修、選択の別 | 必修 |
| 授業形態 | 演習 |
| 到達目標 | 1.基礎演習での学習を基礎として、専門分野に対する学習意欲を高める。
2.卒業レポート作成に向けての論理的な思考力、文章力、表現力等を養う。 3.教育や福祉についての知識・技術を習得する。 4.保育者に必要な情報リテラシーを習得する。 5.数理・データサイエンスの基礎を学ぶ。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 本演習は、基礎演習での学習を発展させ、学生自らがテーマを設定し、主体的な研究を進め、「卒業演習Ⅱ」における卒業レポート・卒業制作へとつなげていくものである。また、情報リテラシーを身に付け、数理・データサイエンスの基礎を学ぶことで種々の情報を分析、評価、整理、活用する方法を学ぶ。
本演習は、本学の特色ある科目として、卒業必修科目の一つとなっており、学生一人一人の個性の伸長と専門分野に関わる学習の深化に力点をおいている。 本授業は、状況によってオンライン教材等を用いた遠隔授業を行う。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | オリエンテーション | データサイエンスの導入
・専門職で働くことに注目したデータサイエンスの役割 ・データ分析の対象や目的の設定 ・データサイエンス教育と社会の応用事例 使用テキスト:はじめてのデータサイエンス(学術図書出版) |
| 2回 | 数理・データサイエンス・AIの基礎(1) | 社会で活用されているデータ
・「データ」とはなにか、データの種類 ・実際のデータの入手方法や解析方法の基本 ・復習テスト(10問) 事前学習:資料の熟読(30分) 事後学習:PCを使っての課題(60分) |
| 3回 | 数理・データサイエンス・AIの基礎(2) | データの活用領域
・「データサイエンス」とは何か ・グループ内発表 ・ディスカッション:テーマ「データ、AIの活用領域の広がり、どのような分野でデータサイエンスが取り入れられているか、今後データサイエンスを取り入れるとよりよくなる可能性がある分野は何か」 ・データサイエンスのサイクル ・様々な分野におけるデータサイエンスの活用事例 ・活用事例の課題説明 ・復習テスト(1-5の内容を含めて10問) 事前学習:資料の熟読(30分) 事後学習:PCを使っての課題(60分) |
| 4回 | 数理・データサイエンス・AIの基礎(3) | 様々なデータの種類とその読み方
・データの種類(量的変数、質的変数) ・データの分布(ヒストグラム)と代表値(平均値、中央値、最頻値) ・代表値の静謐の違い ・データのばらつき(分散、標準偏差、偏差値) ・打ち切りや脱落を含むデータ、層別の必要なデータ ・相関と因果(相関係数、疑似相関、交絡) ・母集団と標本抽出(国勢調査、アンケート調査、全数調査、単純無作為抽出、層別抽出、多段抽出) ・クロス集計表、分割表、相関係数行列、散布図行列 ・データの比較(条件をそろえた比較、処理の前後での比較、A/Bテスト) ・統計情報の正しい理解(誇張表現に惑わされない) ・復習テスト(10問) 事前学習:資料の熟読(30分) 事後学習:PCを使っての課題(60分) |
| 5回 | 研究方法(1)
|
卒業レポートの書き方(目的、方法、結果、考察)についての学習
事前学習:過去の卒業レポートの熟読(30分) 事後学習:自身の研究についての考察(60分) |
| 6回 | 数理・データサイエンス・AIの基礎(4) | 様々なデータの表現・集計方法のエクセルを使っての演習
・データ表現(棒グラフ、折れ線グラフ、散布図) ・データの図表表現(チャート化) ・不適切なグラフ表現(チャートジャンク、不必要な視覚的要素) ・優れた可視化事例の紹介 ・基本統計量を求める ・相関係数を求める ・検定の考え方と平均値の差の検定 ・復習テスト(10問) 事前学習:資料の熟読(30分) 事後学習:PCを使っての課題(60分) |
| 7回 | 数理・データサイエンス・AIの基礎(5) | 様々なデータ活用事例
・今のAIでできることとできないこと ・AIとビックデータ ・特殊型AIと汎用AI ・復習テスト(10問) 事前学習:資料の熟読(30分) 事後学習:PCを使っての課題(60分) |
| 8回 | 数理・データサイエンス・AIの基礎(6) | プログラミングの基礎についての学習
・復習テスト(10問) 事前学習:資料の熟読(30分) 事後学習:PCを使っての課題(60分) |
| 9回 | 研究方法(2) | 研究テーマに関する情報収集・探索法の学習
事前学習:研究関連書籍の熟読(60分) 事後学習:自身の研究についての考察(30分) |
| 10回 | 数理・データサイエンス・AIの基礎(7) | 情報セキュリティーについての学習
・情報セキュリティー(気密性、安全性、可用性) ・匿名加工情報と暗号化、パスワード、悪意のある情報搾取 ・情報漏洩等によるセキュリティー事故の事例紹介とグループディスカッション ・個人情報の保護、EU、一般データ保護規則、忘れられる権利、オプトアウト ・データ倫理(データの捏造、改ざん、盗用、プライバシーの保護) ・AI社会原則(公平性、説明責任、透明性、人間中心の判断) ・復習テスト(10問) 事前学習:資料の熟読(30分) 事後学習:PCを使っての課題(60分) |
| 11回 | 予備的研究(1) | 研究テーマの検討・決定
事前学習:研究関連書籍の熟読(60分) 事後学習:自身の研究についての検討(30分) |
| 12回 | 予備的研究(2) | 調査方法(実験・実習法、製作法)の検討、調査表の作成
事前学習:調査法の検索(60分) 事後学習:具体的な研究方法の検討(30分) |
| 13回 | 予備的研究(3) | 調査の実施、実験・実習、製作法の決定
結果の処理方法の学習 事前学習:調査のための準備(60分) 事後学習:調査結果についての検討(60分) |
| 14回 | 研究方法(4) | 発表の方法(プレゼンテーション技法等)についての学習
事前学習:先行研究者のレポートの熟読(60分) 事後学習:プレゼン関係などの書籍を活用しまとめる(60分) |
| 15回 | 総括講義
卒業レポートゼミ内発表会 |
課題、発表等に対するフィードバックを行う
1,2年生合同ゼミ内発表 発表内容に対するディスカッションを行い技法などを学習する 事前学習:発表者作成資料の熟読(60分) 事後学習:発表から学習した事項をまとめる(60分) |
| 16回 | 卒業レポート発表会 | 卒業レポート発表会の参加
事前学習:要旨集の熟読(60分) 事後学習:発表内容から自身のレポートに活用させる(60分以上) 授業評価 |
| 成績評価の方法・基準 | 授業態度50%、資料作成25%、提出物25% |
|---|---|
| 教科書・参考書 | 滋賀大学データサイエンス学部・山梨学院大学ICTリテラシー教育チーム共編「はじめてのデータサイエンス」学術図書出版 |
| 履修条件 | なし |