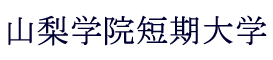子ども家庭支援論
田中結香
2単位
保育科
| 履修系統図番号 | 9C-2025 |
|---|---|
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 必修、選択の別 | 選択 保育士必修 |
| 授業形態 | 講義 |
| 到達目標 | 1.保育者として子ども家庭支援策の意義と内容について理解し説明することができる。
2.保育者としての対人援助の理念と基本的技術であるソーシャルワークについて理解し説明することができる。 3.障がいや貧困,不適切養育環境等やその家庭についての現状と課題を理解し支援体制が説明できる。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 保育者は子どもの支援のみではなく、子どもの家庭に対する支援者としての立場が求められる。そのため、地域社会の中で家庭がどのような状況にあるのかを的確に把握するとともに、対人援助の基本的技術、子ども・子育て支援の具体的内容を学ぶ。対人援助技術の習得では、グループワーク、ディスカッションを取り入れた授業を展開する。
本講義は,地域包括支援センター・在宅介護支援センター・病院・行政の社会福祉士,精神保健福祉士,介護支援専門員としての実務経験を持つ教員が,社会福祉各分野における現状と基礎理論,福祉の実施体制等の実際について指導する。 本講義は,状況によってオンライン教材等を用いた遠隔授業を行う。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | オリエンテーション
子ども家庭支援論の学修目的の確認 |
・子ども家庭支援について、これまで学修してきた科目と連動させて理解する
事前学習:これまで学修してきた「社会福祉」「子ども家庭福祉」「社会的養護」の科目の振り返り(90分) 事後学習:子ども家庭福祉と他の科目との関連する点をまとめる(120分) |
| 2回 | 第1章 子どもと家庭を取り巻く環境
1)家族と家庭 2)家族・家庭を取り巻く環境 3)子どもをもつ家庭を取り巻く環境 |
・子どもと家庭を取り巻く環境について理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:子どもをもつ家庭を支援する意義についてまとめる(150分) |
| 3回 | 第2章 保育者が実践する子ども家庭支援とは
1)子ども家庭支援の基本的考え方 2)子ども家庭支援の基本的視点 3)保育者の専門性を生かした支援 |
・子ども家庭支援の基本的な視点と専門性を生かした支援の必要性について理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:保育者が子ども家庭支援の中心的な役割を担う必要性についてまとめる(150分) |
| 4回 | 第3章 子育て家庭を支える法・制度および社会資源
1)子育て家庭を支える法・制度 2)子育て家庭を支える社会資源 |
・子ども家庭を支える法制度や社会資源について理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:自身が暮らしている市町村の子育て支援に関するプランや計画について調べて内容をまとめる(150分) |
| 5回 | 第4章 保育者に求められる基本的態度及び基本技術
1)相談を受ける者の基本的態度 2)相談場面で必要な技術 3)保育現場での相談スキルの活用場面 |
・ソーシャルワーク技術を理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:教科書の事例についてどのように支援していくとよいか,ソーシャルワーク技術の活用を含めて考察する(150分) |
| 6回 | 第5章 保育者が行う子ども家庭支援の実際
1)保育所等の特性を生かす 2)保育場面における具体的な子育て支援の方法 |
・保護者とのコミュニケーションの取り方を通じた保護者支援の方法について理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:保育者がどのように子育て支援に関われるかについてまとめる(150分) |
| 7回 | 第6章 地域の子育て家庭への支援
1)保育所等が行う地域子育て支援 2)関係機関との連携・協力事例 3)地域子育て支援専門職としての支援の実際と取り組み |
・地域子育て支援における保育者の役割を理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:地域の子育て家庭の支援を実施する上で必要な連携機関と方法についてまとめる(150分) |
| 8回 | 第7章 さまざまな子ども家庭の理解と支援
1)子ども家庭のさまざまな形 2)ひとり親家庭における支援の展開 3)新たな親子関係をつくる家庭への支援 4)外国とつながりのある子どもの保育と支援 |
・子ども家庭への様々な形と支援方法を理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:様々な形の家庭への支援について保育者が求めらえる方法についてまとめる(150分) |
| 9回 | 第8章 不適切な養育環境の子どもやその家庭への支援
1)保護者のSOSとしての不適切な養育環境への気づき 2)不適切な養育環境の子どもやその家庭における支援の展開 3)代替養育の理解と家庭への支援 |
・子ども虐待の現状と家庭への支援方法について理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:気になる子どもの保護者と関わる際の技術について保護者理解の支援からまとめる(150分) |
| 10回 | 第9章 発達障がい児等の理解と家庭への支援
1)日本における障がい児に関する現状 2)障がいのある子どもや家庭への支援の展開 |
・発達障がい児の現状と支援方法を理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:障がいの有無にかかわらず,子どもの保育とその家庭を支援することに共通している内容についてまとめる(150分) |
| 11回 | 第10章 子どもの貧困の理解と家庭への支援
1)子どもの貧困とは何か 2)子どもの貧困問題における支援の展開 |
・子どもの貧困の課題と他機関と連携して支援する方法を理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:教科書の事例について,保育者としてどのように関わるかについてまとめる(150分) |
| 12回 | 終章 保育と子ども家庭支援
1)保育が子ども家庭支援に果たす役割 2)子ども家庭支援におけるソーシャルワーク 3)「小学校との接続」と子ども家庭支援 |
・保育が子ども家庭支援に果たす役割を理解する
事前学習:教科書の該当ページの熟読(90分) 事後学習:保育者がなぜ子ども家庭支援が必要なのかについてまとめる(150分) |
| 13回 | 子ども家庭支援における基本的技術①
保育所保育指針 第4章の振り返り |
・保育所保育指針からを子ども家庭支援を理解する
事前学習:保育所保育指針の内容を復習する(90分) 事後学習:保育所保育指針第4章の内容と、これまで学修した内容との関連についてまとめる(150分) |
| 14回 | 子ども家庭支援における基本的技術②
ソーシャルワークの理解 |
・子ども家庭支援におけるソーシャルワークの必要性を理解する
事前学習:ソーシャルワークとは何かについて復習する(90分) 事後学習:保育者がソーシャルワーク技術のを求められている理由と根拠についてまとめる(150分) |
| 15回 | 定期試験 | |
| 16回 | 総括講義 | ・保育士・幼稚園教諭の視点から,子ども家庭支援の必要性について総合的に考える
・授業評価 ・定期試験の解答説明と振り返り 事前学習:これまでの講義で学んだことをもとに,保育士・幼稚園教諭として「子ども家庭支援」を学ぶ意義について考察し,400字程度でレポートにまとまる。(120分) 事後学習:講義全体を振り返り,保育士・幼稚園教諭として「子ども家庭支援」を学びどのように実践に活かせるかについて考察し,400字程度でレポートにまとめる。(120分) |
| 成績評価の方法・基準 | 筆記試験 60%
課題提出 20% リアクションペーパー 20% |
|---|---|
| 教科書・参考書 | 教科書:
「学ぶ・わかる・みえる 保育と子ども家庭支援論」株式会社みらい発行(¥2,100+税) |
| 履修条件 | 特になし |