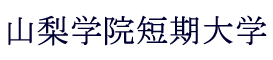食生活学
「何をどれだけ食べればよいか」を考える
深澤早苗
2単位
食物栄養科栄養士コース
| 履修系統図番号 | 3NPC-0208 |
|---|---|
| 科目区分 | 一般基礎教育科目 |
| 必修、選択の別 | 選択 |
| 授業形態 | 講義 |
| 到達目標 | 1.食生活や生活習慣が健康に与える影響について理解する。
2.日本の食の歴史を知り、「和食」についての理解を深める。 3.日常食の基本構成(主食・主菜・副菜)を理解し、日常生活に活用する。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 本講義は、栄養素の役割、食生活や生活習慣が健康に与える影響等について学ぶことを目的としている。また、食事バランスガイドによる食事調査や箸の使い方トレーニング、アルコールパッチテスト等の体験学習を通して、望ましい食生活のあり方についても学習する。
なお、本講義は、状況によって、オンライン教材等を用いた遠隔授業を行う。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | オリエンテーション | 本講義で取り上げるテーマの概説
「食生活学」を学ぶ意義を考える 事前学習のグループディスカッション 事前学習:食生活に関する最新の話題やニュースを調べる(60分) 事後学習:グループディスカッションの内容を整理する(60分) |
| 2回 | 箸のマナー<体験学習> | 箸の持ち方とトレーニング、箸のマナー
事前学習:自分の箸の使い方、家族の箸の使い方について、悪い点を調べる(60分) 事後学習:自分の箸の長さを測る、日常生活で箸のマナーをふりかえる(60分) |
| 3回 | 主食の世界地図 | 主食の世界地図、主食と気候、稲作と麦作の食文化への影響、米と麦の食品学的特徴
事前学習:三大穀物について調べる(60分) 事後学習:穀物の世界地図を仕上げる(60分) |
| 4回 | 日本と中国の食文化 | 日本と中国の食の歴史を辿る
事前学習:和食の特徴を調べる(60分) 事後学習:「醤」についてまとめる(60分) |
| 5回 | 日本の伝統的な食文化(和食、行事食の由来) | 五節供の由来
ビデオ学習:「和食」が日本文化である理由 事前学習:五節供とは何か調べる(60分) 事後学習:和食の精神性についてまとめる(60分) |
| 6回 | 五大栄養素の役割
食物繊維・水の役割 |
五大栄養素、食物繊維、水の体内における役割について考える
事前学習:五大栄養素について調べる(60分) 事後学習:配付プリントの内容を整理する(60分) |
| 7回 | 朝食の役割
食事バランスガイド 自分の食生活診断<体験学習> |
食事バランスガイドの目的と活用、エネルギー必要量の算出
食事バランスガイドを用いた食事調査の実施 事前学習:自分のある1日の食事内容を調べる(60分) 事後学習:食事調査結果から食生活の改善点をレポ―トにまとめる(60分) |
| 8回 | お弁当の作り方<プレゼンテーション> | 「3・1・2お弁当法」の活用
料理カードを使ってお弁当を作り、作ったお弁当をプレゼンテーションする 事前学習:自分のお弁当を写真にとり、その食材を調べる(60分) 事後学習:自分のお弁当箱の容量を測り、不足分の補い方を考える(60分) |
| 9回 | お酒の付き合い方<エタノールパッチテスト> | お酒のアルコール度数と適量、お酒の飲み方
エタノールパッチテストでアルコアール体質を知る 事前学習:アルコール飲料の度数を調べる(60分) 事後学習」:さまざまなアルコール飲料のエタノール10gに相当する量を調べてみる(60分) |
| 10回 | 女性と栄養 | ライフステージと食生活
成年期・妊娠期・高齢期の女性の食生活 事前学習:青年期女性の食生活に関する問題点を調べる(60分) 事後学習:葉酸の多い食品を調べる(60分) |
| 11回 | 骨粗鬆症 | 健康と生活習慣、骨粗鬆症の理解と予防のための食生活
事前学習:骨粗鬆症について調べる(60分) 事後学習:配付プリントの内容を整理する(60分) |
| 12回 | 低栄養<指輪っかテスト> | 栄養の二重負荷、低栄養の現状、フレイル予防
輪っかテスト 事前学習:低栄養について調べる(60分) 事後学習:低栄養を予防するための食生活のあり方についてまとめる(60分) |
| 13回 | 食物アレルギー<グループワーク> | 食物アレルギーの概要、保育所や学校での対応
食物アレルギー症例を通して問題点と対策の検討 事前学習:食物アレルギーを発症する食品について調べる(60分) 事後学習:配付プリントの内容を整理する(60分) |
| 14回 | 保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)
グループワーク |
特別用途食品、保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)
事前学習で調べた特定保健用食品の種類についてグループワークで理解を深める。 事前学習:特定保健用食品の種類、内容について調べる(60分) 事後学習:保健機能食品について、それぞれ種類と内容を調べまとめる(60分) |
| 15回 | 定期試験(レポート提出) | 事前学習:レポート作成に向けてこれまでの復習を行う。(240分) |
| 16回 | 総括講義
|
定期試験の解説と解答
本講義のまとめ 事前学習:提出したレポート内容について見直す。(60分) 事後学習:各回の授業内容のPPを復習する。(60分) |
| 成績評価の方法・基準 | レポート80%、提出課題10%、授業への積極的参加態度10%を総合的に評価する。 |
|---|---|
| 教科書・参考書 | 講義は配布資料をもとに行う |
| 履修条件 | なし |