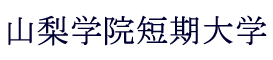家庭科教育法
網倉玉枝
2単位
保育科
| 履修系統図番号 | 8C-2016 |
|---|---|
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 必修、選択の別 | 選択 教職必修(小) |
| 授業形態 | 講義 |
| 到達目標 | 1.小学校家庭科教育の意義、目標を理解する。
2.小学校家庭科の指導に必要な知識及び技能を身に付ける。 3.小学校家庭科の指導方法や評価について学び、指導案を作成し、授業を展開することができる。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 小学校家庭科教育の意義、目標、内容、指導方法、指導計画、学習評価について学習する。指導に必要な基礎的な知識及び技能については、講義のほか、実技、実験、グループワーク等により、体験的に学習する。
学習指導案の作成について学び、それに基づいた模擬授業の実施により、実践的に学習する。 ※小・中学校で家庭科の指導経験をもつ教員が、その経験を生かして家庭科の授業づくりの実際的な理論と方法を指導する。 本講義は、状況によっては、オンライン教材等を用いた遠隔授業を行う。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | ガイダンス
家庭科の意義、理念、目標 |
授業概要と進め方
家庭科教育の意義等の理解 事前学習:学習指導要領を一読してくる。(60分) 事後学習:家庭科教育の意義、理念等に関する演習課題に答える。(60分) |
| 2回 | 家庭科教育の歴史
小・中・高等学校の家庭科の目標・内容と指導計画 |
家庭科教育の歴史、変遷の理解
小・中・高等学校の学習内容の関連性の把握 事前学習:小・中・高等学校の家庭科の目標・内容について調べる。(60分) 事後学習:家庭科教育の歴史に関する演習課題に答える。(90分) |
| 3回 | 教材研究の要点
各領域の目標と内容及び指導展開例① |
教材研究の重要性の理解
「家族・家庭生活」の目標と内容の理解 事前学習:「家族・家庭生活の現状と課題」を読み、気付いたことをまとめる。(90分) 事後学習:「家族・家庭生活」の指導上の配慮点をまとめ、演習課題に答える。(90分) |
| 4回 | 各領域の目標と内容及び指導展開例② | 「食生活」の目標と内容の理解
事前学習:「食生活の現状と課題」を読み、気付いたことをまとめる。(90分) 事後学習:「食生活」の指導上の配慮点をまとめ、演習課題に答える。(90分) |
| 5回 | 各領域の目標と内容及び指導展開例③ | 「衣生活」の目標と内容の理解
事前学習:「衣生活の現状と課題」を読み、気付いたことをまとめる。(90分) 事後学習:「衣生活」の指導上の配慮点をまとめ、演習課題に答える。(90分) |
| 6回 | 各領域の目標と内容及び指導展開例④
|
「住生活」の目標と内容の理解
事前学習:「住生活の現状と課題」を読み、気付いたことをまとめる。(90分) 事後学習:「住生活」の指導上の配慮点をまとめ、演習課題に答える。(90分) |
| 7回 | 各領域の目標と内容及び指導展開例⑤
|
「消費生活・環境」の目標と内容の理解
事前学習:「消費生活・環境の現状と課題」を読み、気付いたことをまとめる。(90分) 事後学習:「消費生活・環境」の指導上の配慮点をまとめ、演習課題に答える。(90分) |
| 8回 | 学習指導計画の作成と内容の取り扱い
学習指導 |
学習指導要領の記述内容の分析と理解
学習指導計画案の作成 学習指導の諸方法の理解 事前学習:学習指導要領の「指導計画の作成と内容の取り扱い」を読み、配慮事項を確認する。(60分) 事後学習:「実験・実習を用いた授業の事例」「五感で学ぶ授業の事例」等をまとめる。(90分) |
| 9回 | 学習評価
|
評価の意義、目的、観点、方法等の理解
評価規準と評価基準の理解 事前学習:小学校家庭科の指導における評価の事例を調べ考察する。(90分) 事後学習:①様々な評価方法、②評価規準と評価基準について整理してまとめる。(60分) |
| 10回 | 施設・設備の整備と安全
学習指導案の作成 |
施設・設備の整備と安全、衛生的な管理の理解
学習指導案の内容と作成上の留意点の理解 事前学習:学習指導要領における「施設・設備の整備と安全、衛生的な管理」に関する記述を読む。(30分) 事後学習:学習指導案を作成する。(120分) |
| 11回 | 学習指導案の作成・検討
|
作成した学習指導案の相互評価とグループディスカッションによる教材研究
事前学習:学習指導案を作成する。(120分) 事後学習:模擬授業の準備(学習指導案の修正、教材作成等)をする。(240分) |
| 12回 | 模擬授業の実施① | 個人またはグループによる模擬授業の実施・相互評価
事前学習:模擬授業の最終確認をする。(90分) 事後学習:授業の相互評価と各自の授業の反省と 改善を行う。(30分) |
| 13回 | 模擬授業の実施② | 個人またはグループによる模擬授業の実施・相互評価
事前学習:模擬授業の最終確認をする。(90分) 事後学習:授業の相互評価と各自の授業の反省と 改善を行う。(30分) |
| 14回 | 模擬授業についての評価と改善
NIE・ICTを活用した学習指導 |
教員の評価に基づいた授業の反省と改善
NIE、ICTを活用した授業についての理解 事前学習:家庭科教育に関する新聞記事を収集し、整理する。(60分) 事後学習:ICTを利用した学習指導についてまとめる。(60分) |
| 15回 | 定期試験 | 事前学習:試験に備えての学習(240分)
事後学習:試験結果の自己採点(30分) |
| 16回 | 総括講義 | 本講義のまとめと評価
定期試験の解説と総評 授業評価の実施 事前学習:「家庭科教育の展望」を読む。(60分) 事後学習:学習成果の確認(30分) |
| 成績評価の方法・基準 | 定期試験(筆記)60%、課題提出状況と内容等40%を目安に総合的に評価する。 |
|---|---|
| 教科書・参考書 | 教科書:「小学校家庭科教育法」大竹美登利・鈴木真由子・綿引伴子(建帛社)(\2530)
「小学校教科書「わたしたちの家庭科」 (開隆堂)(\288) 参考文献:「小学校学習指導要領」(文部科学省) 「小学校学習指導要領解説 家庭編」(文部科学省) 「中学校学習指導要領」(文部科学省) 「高等学校学習指導要領」(文部科学省) |
| 履修条件 | 小学校教職課程履修者 |