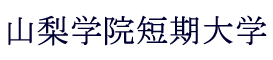食事設計実習
深澤早苗・鈴木睦代・関戸元恵
1単位
食物栄養科栄養士コース
| 履修系統図番号 | 10N-1020 |
|---|---|
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 必修、選択の別 | 選択 栄養士必修 |
| 授業形態 | 実習 |
| 到達目標 | 1.食事摂取基準を活用して、対象者に応じた食事基準を示すことができる。
2.食品成分表を食事計画(献立作成)に活用できる。 3. 日常食の基本構成(主食、主菜、副菜)を理解し、食品の組み合わせや使用量を説明できる。 4.調味パーセントを活用できる。 5.献立を立案して栄養価を正しく算出でき、その結果を評価できる。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 献立作成は栄養士の主要業務の1つである。集団給食ならびに栄養指導時に作成する
献立は、「栄養的」、「経済的」、「嗜好的」に配慮されたものでなければならない。 本実習は、献立を作成するにあたって必要となる基礎知識や技術を習得し、献立が作成 できることをねらいとする。授業は献立作成の手順にそって進める。 本授業は、状況によって、オンライン教材等を用いた遠隔授業を行う。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | ガイダンス(授業内容の説明)
食事バランスガイドの概要 日本食品標準成分表とその使用方法Ⅰ |
食事バランスガイドの内容と活用法
食品成分表の概要 穀類からきのこ類までの食品の特徴 |
| 2回 | 日本食品標準成分表とその使用方法Ⅱ | 食品成分表の概要とその使い方
藻類から調理加工食品類までの食品の特徴 |
| 3回 | 日本人の食事摂取基準2020年版の概要
小テスト(食品成分表) |
食事摂取基準の意義や特徴、基準量の求め方、使い方
|
| 4回 | 食品構成と食品群別使用量
小テスト(食事摂取基準) |
食品構成の意味と分類法、食品群別使用量の算出方法
|
| 5回 | 献立作成の基本Ⅰ
一日分の献立作成(対象:成人女子) 小テスト(食品群別使用量) |
献立の意味、構成、作成の手順、留意点
事後学習:一日分の献立(献立名、食品名のみ)を作成する(180分) |
| 6回 | 献立作成の基本Ⅱ
|
献立重量の決め方
事後学習:一日分の献立(献立名、食品名、重量)を作成する(180分) |
| 7回 | 調味割合の基本Ⅰ(塩分と糖分の求め方) | 調味割合の意味と利点、塩分と糖分の調味料重量の算出法
事後学習:一日分の作成献立の塩分と糖分の調味料重量を算出する(180分) |
| 8回 | 調理割合の基本Ⅱ | 調味割合の意味と利点、調味料重量の算出法
事後学習:一日分の作成献立の全ての調味料重量の算出および調味割合を算出する(180分) |
| 9回 | 献立指導
小テスト(調味割合) |
作成献立の調味料重量および調味割合の見直し、作成献立の食品群別使用量の算出
|
| 10回 | 栄養価計算の方法 | 栄養価算出の目的、栄養価算出の方法
事後学習:作成した献立の栄養価計算をする(270分) |
| 11回 | 献立の評価方法
小テスト(栄養価計算) |
栄養比率の目的、栄養比率の算出方法
事後学習:作成した献立の栄養比率を算出する(180分) |
| 12回 | 献立指導
小テスト(献立の評価) |
作成献立の重量、栄養価計算、調味量重量、調味割合の見直し |
| 13回 | 購入量と価格の求め方
小テスト(購入量と価格) |
購入量および価格の算出方法
事後学習:作成した献立の購入量および価格を算出する(180分) |
| 14回 | 到達度テスト | 食事摂取基準から価格まで献立作成に必要な項目の算出方法についての習得度確認
事前学習:学習内容の復習(270分) |
| 15回 | 総括講義
到達度テスト(再テスト) 作成献立の提出 |
到達度テストの解説と講評
本実習のまとめ |
| 成績評価の方法・基準 | 献立作成に必要な知識についての到達度テスト90%、レポート(献立作成)10%
到達度テストは100点満点中60点以上の正答を求める。60点に満たない場合は、再試験を実施する。 |
|---|---|
| 教科書・参考書 | 深澤早苗、鈴木睦代、大柴由紀、秋山有佳著『食事設計実習』山梨学院栄養指導研究会2025年(¥1,200)
『食品解説つき八訂準拠ビジュアル食品成分表』大修館書店2025年(¥1,400) |
| 履修条件 | なし |