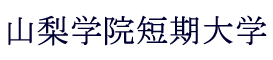保育内容特論(言葉)
佐藤喜美子
1単位
専攻科保育専攻
| 履修系統図番号 | 8A-2055 |
|---|---|
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 必修、選択の別 | 選択 教職必修(幼) |
| 授業形態 | 演習 |
| 到達目標 | 1:幼稚園教育要領に示された幼稚園教育の基本を踏まえ、領域「言葉」のねらい及び内容を理解する。
2:言葉の育ちににかかわる様々な活動を理解し、保育・教育の場面で活用する力を、身に付ける。 3:演習を通して領域(言葉)の指導の実践力を付ける。 4:スタートカリキュラムを領域言葉の視点から考えることができる。 現行「小学校学習指導要領」「教育要領・保育指針・教育指針」の方向性や、幼児期が終わるまでに育ってほしい10の姿を見据えて、保育内容(言葉)の領域を再確認する。AL(主体的・対話的で深い学び)の礎となる、幼児期の言葉の育ちの重要性や スタートカリキュラム・架け橋プログラムなどを意識して、幼児期の言葉の発達と育成のための保育者・教育者として、言葉に関わる『資質・能力』の向上を実践的に身に付ける。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 次の学びを通して、言葉の指導に当たる保育者・教育者としての『資質・能力』の
向上を図る。 ①現行の教育要領や保育指針等の方向性の確認と、教育者・保育者としての資質・能力の確認。 ②言葉に対する感覚を豊かにするための、様々な演習を通しての実践力を磨く。 ○絵本などを活用した演習 ○ビブリオバトルの演習 ○リテラチャーサークルの演習 ○アニマシオンの演習 ○絵本の読み語りの技能 ③スタートカリキュラムの作成と情報機器を活用した演習と振り返り。 なお、本授業は、状況によって、オンライン等を用いた遠隔授業を行う。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | 教育者・保育者としての資質・能力について
スタートカリキュラム・架け橋プログラムについての理解 領域「言葉」のねらいと内容について |
・現行の小学校学習指導要領国語 教育要領 保育指針等の領域言葉の方向性の確認
・参考資料として提示する『通信』を読んで通信にはどのようなことを書くのか理解する 事後学習=スタートカリキュラムを構想する オリジナル「お便り」の作成(120分) |
| 2回 | 幼児の言葉の育ちと幼児の主体性・対話性を引き出す言葉掛け
|
・『こんなときこんな言葉掛けで子どもがこう変わった』実践事例交流・ワールドカフェ方式で行う
事前学習=これまでの現場実践から自分が蓄積した言葉がけをまとめてくる (120分) 事後学習=学びのまとめとして通信を書く(120分) |
| 3回 | 幼児の言葉の育ちと支援の在り方 | DVD「こどもの「ことば」~保育現場での成長・発達~」を視聴し、言葉と幼児の体験と支援の在り方について話し合い、よりよい保育を構想する
事前学習=『新編子どもの図書館』石井桃子著 及び『子どもと子どもの本に捧げた生涯 瀬田貞二先生について』斎藤惇夫著に目を通してくる(120分) 事後学習=学びのまとめとして通信を書く(120分) |
| 4回 | 言葉に対する感覚を豊かにする保育構想(演習)
アニマシオンの実践を通して |
絵本などを活用した保育構想
(グループワークで交流 見合い 聞き合い、相互批評し、よりよい保育について話し合う 事前学習=絵本を活用した保育実践演習:アニマシオンを考えてくる(120分) 事後学習=学びのまとめとして通信を書く(120分) |
| 5回 | 言葉に対する感覚を豊かにする保育構想(演習)
リテラチャーサークルの実践を通して |
言葉遊び アニマシオンなどを活用した保育構想
(グループワークで交流 見合い 聞き合い、相互批評し、よりよい保育について話し合う 事前学習=リテラチャーサークル演習の為の読書(120分) 事後学習=学びのまとめとして通信を書く(120分) |
| 6回 | 領域(言葉)を意識して構想した保育の指導計画案の作成
ビブリオバトルの実践を学ぶ |
模擬保育をグループワークで構想し、共同指導案を作成する
事前学習=自分で構想した保育の指導案を書いてくる(120分) 事後学習=模擬保育指導案の完成と学びのまとめとして通信を書く(120分) |
| 7回 | 領域(言葉)を意識した模擬保育の演習と振り返り(評価の考え方を含む)
言葉あそび (早口言葉 オノマトペ なまえ遊び 言葉探し等) |
自分で考えた模擬保育の演習
相互に見合い、よりよい保育について話し合う 評価について考える 事前学習=自分で構想した模擬保育演習の準備をする(120分) 事後学習=これまでの学びをスタートカリキュラムとつなぐ(120分) |
| 8回 | 総括講義
自分で考えたスタートカリキュラムの交流とディスカッション 授業評価アンケート |
事前学習=言葉の領域との重なりについて意識したスタートカリキュラムを構想して提出(240分)
本講義のまとめ:課題や演習についての講評 事後学習=本演習の学びを今後にどう活かすかを見通す 小学校とのつながりを考える(120分) |
| 成績評価の方法・基準 | ①毎回の課題と試験レポート【スタートカリキュラムの作成】(50%)
②グループワーク演習等の資質・技能(40%) ③出会いの日に発信する『おたより』の内容と書きぶり(10%) 以上により評価・評定を行う |
|---|---|
| 教科書・参考書 | ○必要な資料は随時配付します。
☆参考文献は次の通り 厚生労働省「保育所保育指針」 文部科学省「幼稚園教育要領」 内閣府・文部科学省・厚生労働省「幼保連携型認定こども園教育・保育要領 厚生労働省「保育所保育指針解説書」 文部科学省「幼稚園教育要領解説」 内閣府・文部科学省・厚生労働省「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」 学びで使う参考文献は次のとおりです。各自図書館や公共図書館で借りて読んでくる ①『新編子どもの図書館』石井桃子著 岩波現代文庫 ②『子どもと子どもの本に捧げた生涯瀬田貞二先生について』斎藤惇夫著キッズメイト ③児童文学論(石井桃子著) ④幼い子の文学(瀬田貞二著) ⑤本・子ども・大人(ポールアザール著 矢崎源九郎・横山正矢共訳) これ以外のアニマシオン等々の本は、』実物を提示します。 |
| 履修条件 | なし |