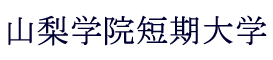保育実習指導Ⅱ(保育所)
中込まゆみ・川上英明
1単位
保育科
| 履修系統図番号 | 11C-2050 |
|---|---|
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 必修、選択の別 | 保育士選択必修 |
| 授業形態 | 演習 |
| 到達目標 | 1 保育実習Ⅱの意義と目的を理解し、保育について総合的に理解している。
2 実習や既習の教科目の内容やその関連性を踏まえ、保育の実践力を習得している。 3 保育の観察、記録及び自己評価等を踏まえた保育の改善について、実践や事例を通して理解している。 4 保育士の専門性と職業倫理について理解している。 5 実習の事後指導を通して、実習の総括と自己評価を行い、対する課題や認識を明確に保育に説明することができる。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 本科目は、学外の保育所での実習により、実践的教育を行う授業である。教科において習得した知識、技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用能力を養うため、幼児に対する理解を通じて保育の理論と実践の関係について習熟させることを目的とする。
実際に保育所で専門的な知識・技能を生かしながら子どもに関わることを通じて、子どもの理解を深め、保育を実践できる総合的な力を養う。 授業は演習形式で進めていくことを基本とするが、学修内容に合わせて適宜、グループワークやディスカッションなども取り入れて行う。 *※本教科担当中込は、保育士資格を有して、長年の現場経験を有する教員である。 本講義は、状況によりオンライン教材等を用いた遠隔授業を行う。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | 保育実習Ⅱの意義・目的・内容
担当:中込・川上 |
・実習の目的
・実習の内容 ・実習の自己課題の確認 事前学習:既に取り組んだ実習(幼稚園・保育所・施設を含む)日誌を読み直し、振り返りを行う。(60分) 事後学習:配付プリント内容の確認(60分) |
| 2回 | 保育実習による総合的な学び(グループワーク)
担当:中込・川上 |
・実習園の方針、立地、条件の比較
事前学習:幼稚園・保育所・認定こども園の違いを踏まえて、2年次で行う実習の自己課題について検討する。(60分) 事後学習:配付プリント内容の確認(60分) |
| 3回 | 実践力の育成①子どもとの適切な関わり(グループワーク)
担当:中込・川上 |
・実習中における子どもとのかかわり(遊びと環境構成)
事前学習:実習で配属される年次の理解を深め、遊びおよび環境構成について考える。(30分) 事後学習:部分、責任実習における環境構成について図化してみる。配布資料確認(30分) |
| 4回 | 実践力の育成②保育の知識・技術の実践への活かし方・教材作成
担当:中込・川上 |
・部分実習、責任実習の実際
・保育技術を活かした実践 事前学習:実習Ⅰの実習記録の見直し、指導案の見直し等を行う(30分) 事後学習:配付プリント内容の確認(90分) |
| 5回 | 保育所における計画と実践(グループワーク)
担当:中込・川上 |
・実習における計画と実践
事前学習:1年次での実習の様子を思い出し、実習に望んでの自己イメージを作る。失敗した点、学びになった点などを洗い出しておく。(90分) 事後学習:配付プリント内容の確認(90分) |
| 6回 | 保育現場の映像の視聴
デイリープログラムの作成 担当:中込・川上 |
・デイリープログラムの作成(指導案作りを意識ながら指導の組み立て方を学ぶ)
事前学習:1年次の実習記録の見直し、実習記録の「実習日誌」の項を学習する。(30分) 事後学習:デイリープログラムの清書(30分) |
| 7回 | デイリープログラムの添削、確認(グループワーク)
担当:中込・川上 |
・他者の指導案の添削と確認
事前学習:デイリープログラムの清書(30分) 事後学習:作成したデイリープログラムの訂正・確認(30分) |
| 8回 | 模擬保育の指導案作成
担当:中込・川上 |
・部分実習を仮定し指導案作成
事前学習:年次、ねらい、活動内容について考える。(30分) 事後学習:作成した指導案に加筆および修正 (30分) |
| 9回 | 模擬保育の練習
担当:中込・川上 |
・立案した模擬保育の指導案に沿っの実践練習
事前学習:準備物等の用意(30分) 事後学習:発表に向けての準備(30分) |
| 10回 | 模擬保育実践①(グループワーク)
担当:中込・川上 |
・グループごとに模擬授業の実践
事前学習:発表練習(30分) 事後学習:振り返りレポートの作成(30分) |
| 11回 | 模擬保育実践②(グループワーク)
担当:中込・川上 |
・グループごとに模擬授業の実践
事前学習:発表練習(30分) 事後学習:振り返りレポートの作成(30分) |
| 12回 | 専攻科生よりアドバイス
担当:中込・川上 |
・先輩から、実際の実習の具体的な経験について聞き、理解を深める。
事前学習:実習先にについて調べ質問を考える(30分) 事後学習:先輩の体験と自らの実習について考える、レポートの作成(30分) |
| 13回 | 観察・記録・自己評価と保育の改善(グループワーク)
担当:中込・川上 |
・実習における観察
・実習記録の方法と評価 事前学習:同じ地域での実習にとりくむ仲間と連携をして、実習に向けた課題や連絡事項などを確認しておく。(30分) 事後学習:配付プリント内容の確認(30分) |
| 14回 | 保育実習Ⅱの総括と評価
担当:中込・川上 |
・子どもの人権と最善の利益の考慮
・プライバシーの保護と守秘義務 ・実習生としての心得 事前学習:実習日誌を読み、子どもの人権と最善の利益に関して、あた守秘義務など保育者倫理に関することなどを含め、確認しておく。また、具体的な遊びの展開事例やその指導案などを集め学習しておく(30分) 事後学習:配付プリント内容の確認(30分) |
| 15回 | 保育者としての自己評価と課題の設定
担当:中込・川上 |
・実習の総括と自己評価
・今後の自己課題の明確化 事前学習:事後学習シートの記入(30分) 事後学習:自らの実習を振り返り(30分) |
| 16回 | 実習の振り返りと専門職への出発
担当:中込・川上 |
・保育実践の分析
・自己課題の検討 事前学習:保育者としての自己の課題を、実習の経験を踏まえて考える。(30分) 事後学習:これからともに保育に取り組む保育の仲間の自己課題を踏まえて、自身の保育についての課題意識を深める。(30分) |
| 成績評価の方法・基準 | 提出物の内容と提出状況、授業への参画度・貢献度などを総合的に評価する。 |
|---|---|
| 教科書・参考書 | 実習園の指導者の指示による。
『保育所保育指針解説』 『幼保連携型こども園教育・保育要領解説』 |
| 履修条件 | ・本学実施の実力養成試験で一定基準を満たすこと。
・実習時期までに開講されている保育士資格の必修科目の単位を修得すること。 ・履修すべき実習科目の成績等が適当であること。 |