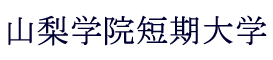臨床栄養学実習
青木慎悟
1単位
食物栄養科栄養士コース
| 履修系統図番号 | 8N-2010 |
|---|---|
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 必修、選択の別 | 選択 栄養士必修 |
| 授業形態 | 実習 |
| 到達目標 | この授業が終了したときに、受講者の皆さんが次のような知識、技能を身につけることを到達目標とします。
1.栄養成分別コントロール食(エネルギー・糖質・脂質・たんぱく質・食塩)の適応疾患に対応する献立の作り方を習得し、実践することができる。 2.摂食機能低下に対応する食形態と調理方法を習得し、実践することができる。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 学修内容:人の健康と食は密接に関わるため、疾患に対応する食事の提供は、治療の視点から重要である。本実習では、傷病者に対する適切な臨床栄養管理の方法について学ぶことを目的としている。具体的には、栄養成分のコントロールの方法について献立の展開を通して理解すること、制約の多い治療食を調理法等の工夫により、喫食者に喜ばれる食事として提供できる力を養うことを目指している。
担当教員の背景と関連した学び:本教科の担当者は、急性期病院における管理栄養士業務(栄養管理や栄養指導等)の経験を有している。その経験をふまえ、講義内では実際の病院における展開食を模した実習や献立作成課題を行っている。また、学修内容の理解を深めるため、学生献立に基づく実習と、関連した栄養教育媒体(プレゼンテーション)を作成し、発表するアクティブ・ラーニング課題も実施している。 ※本授業は、状況によって、オンライン教材等を用いた遠隔授業を行います。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | ガイダンス
臨床調理の基本(教科書第1~3章に対応) 「The Japan Diet」と食事アセスメント課題の説明 |
本実習の到達目標1、2について理解する。
到達目標1の達成を目標に、臨床調理の基本と展開食の実際について学修する。 課題:1日分の食事記録を行い、「The Japan Diet」のチェックシートを用い、食事アセスメントを行う。 |
| 2回 | 大量調理における臨床調理 | 到達目標1、2の達成を目標に主体的に調理実習に取り組む。スチームコンベクションオーブンを用いて、展開食を同時に調理する方法について学修する。 |
| 3回 | 糖尿病食品交換表の概要と活用
・糖尿病食品交換表の食品分類と単位 ・献立の単位算出と献立の展開法 |
到達目標1の達成を目標に、糖尿病食品交換表と糖尿病の食事療法について学修する。
課題:「The Japan Diet」の食事の特徴をふまえて、展開食の元となる常菜食献立を作成する |
| 4回 | エネルギーコントロールのための調理(教科書第3,4章に対応) | 到達目標1の達成を目標に主体的に調理実習に取り組む。エネルギーバランス食、低エネルギー食について学修する。 |
| 5回 | 食塩を減らすための調理(教科書第3,4章に対応) | 到達目標1の達成を目標に主体的に調理実習に取り組む。減塩食の調理(常食との比較、美味しく作る工夫)について学修する。 |
| 6回 | 脂質コントロールのための調理(教科書第3,6章に対応) | 到達目標1の達成を目標に主体的に調理実習に取り組む。低脂質食、脂質の質のコントロール食の調理について学修する。
課題:常菜食献立を糖尿病食に展開する |
| 7回 | たんぱく質コントロールのための調理(教科書第3,5章に対応) | 到達目標1の達成を目標に主体的に調理実習に取り組む。低たんぱく食の調理(常食との比較、エネルギーアップの工夫、たんぱく調整食品の活用)について学修する。 |
| 8回 | その他の栄養素と調理(教科書第3,8章に対応) | 到達目標1の達成を目標に主体的に調理実習に取り組む。カルシウム、鉄、カリウム、食物繊維に着目した調理について学修する。 |
| 9回 | 糖尿病と食事療法と糖尿病献立の作成1 | 到達目標1の達成を目標に主体的にグループ活動に取り組む。グループごとに、「チャレンジ!糖尿病いきいきレシピコンテスト」に準じた糖尿病レシピの作成を行う。作成したレシピは第14回の「学生献立実習」にて、実際に調理を行う。 |
| 10回 | 糖尿病と食事療法と糖尿病献立の作成2 | 第9回に引き続き、到達目標1の達成を目標に主体的にグループ活動に取り組む。作成した糖尿病レシピと関連した栄養教育媒体(プレゼンテーション)を作成する。作成した媒体は第14回の「学生献立実習」にて発表する。 |
| 11回 | 軟菜食のための調理(教科書第2,7章に対応) | 到達目標2の達成を目標に主体的に調理実習に取り組む。軟菜食、きざみ食、ミキサー食の調理について学修する。
課題:常菜食献立を減塩食に展開する |
| 12回 | 摂食調整食のための調理(教科書第2,8章に対応) | 到達目標2の達成を目標に主体的に調理実習に取り組む。ソフト食、嚥下食の調理(食形態の工夫)について学修する。 |
| 13回 | 特別実習:臨床調理の実際 | 到達目標1、2の達成を目標に主体的に調理実習に取り組む。介護老人福祉施設の管理栄養士をお招きし、臨床調理の実際について学修する。
課題:実習内容をまとめ、レポートを作成する。 |
| 14回 | 学生献立実習 | 到達目標1の達成を目標に主体的に調理実習に取り組む。第9、10回で作成した糖尿病レシピの調理を行う。
課題:実習内容をまとめ、レポートを作成する。 |
| 15回 | 定期試験 | レポート・献立提出 |
| 16回 | 総括講義
レポート返却、授業評価アンケート等 |
第14回で作成した献立および栄養教育媒体の相互発表を行う。その後、レポート・献立課題および実習全体に関する講評を行う。
到達目標1、2の達成度について、自己評価を行う。 |
| 成績評価の方法・基準 | 献立等提出物:60%
ミニレポート:20% グループワーク、授業への積極的な参加、実習中の身だしなみ:20% 上記を目安に、出席状況等を含め総合的に評価する。 |
|---|---|
| 教科書・参考書 | 教科書
「臨床栄養学実習書 第13版」¥2900(+税) ※1年次前期開講科目「臨床栄養学総論」にて購入済み。 「糖尿病食事療法のための食品交換表 第7版」¥900(+税) 参考文献 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」厚生労働省 |
| 履修条件 | 履修条件はなし。
ただし、学習内容が相互に関連することから、 1年次に臨床栄養学総論を、2年次に臨床栄養学各論を合わせて履修することが望ましい。 |