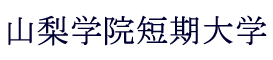臨床栄養学総論
青木慎悟
2単位
食物栄養科栄養士コース
| 履修系統図番号 | 8N-1015 |
|---|---|
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 必修、選択の別 | 選択 栄養士必修 |
| 授業形態 | 講義 |
| 到達目標 | この授業が終了したときに、受講者の皆さんが次のような知識、技能を身につけることを到達目標とします。
1.臨床現場における栄養士の役割と意義について説明することができる。 2.「栄養ケア・マネジメント」について説明することができる。 3.食事調査結果を踏まえて、栄養指導案を作成し、プレゼンの形で発表することができる。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 学修内容:栄養アセスメントの指標として用いられる身体計測、生理・生化学検査、臨床診査、食事・食行動などの各種調査法の理論及び評価方法について科学的に理解する。さらに、身体部位別の疾病・症状、検査値、疾病と栄養の関係について、症例を通して習得し、医療従事者として、傷病者の病態や栄養状態の特徴に基づいた適切な栄養管理・栄養療法の進め方について学ぶ。
担当教員の背景と関連した学び:本教科の担当者は、急性期病院における管理栄養士業務(栄養管理や栄養指導等)の経験を有している。その経験をふまえ、講義内では学習内容の理解を深めるための症例検討を実施している。また、栄養ケア・マネジメントの流れを実践的に学ぶために、食事調査結果を基に栄養管理計画を作成し、相互に発表するアクティブ・ラーニング課題も実施している。 ※本授業は、状況によって、オンライン教材等を用いた遠隔授業を行います。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | ガイダンス
これまでの学習と臨床栄養学とのつながり(教科書:第1章に対応) ★アクティブ・ラーニング課題(食事調査結果をふまえた栄養管理計画の作成)について |
この授業の到達目標1~3について確認する。
到達目標1の達成を目標に、臨床栄養学の意義・目的、栄養アセスメント(食事調査)の概要を学修する。 事前学習:本講義内容と関連する1年前期科目「栄養学総論」「食事設計実習」の講義内容、定期テストの復習を行う(30分) 事後学習:食事調査対象者を決定し、調査への協力を依頼する。得られた食事調査用紙に記入漏れ等がないか確認する。(60分) |
| 2回 | 臨床栄養の概念、病院の仕組み(教科書:第1章に対応) | 到達目標1の達成を目標に、臨床栄養学の意義・目的、栄養ケア記録の特徴について学修する。
事前学習:該当部分の教科書を通読し、赤字の用語の意味を調べておく(30分) 事後学習:学習内容の復習及び演習問題の解答(60分) |
| 3回 | 栄養・食事療法、栄養補給法1「経口栄養補給法」(教科書:第1,2章に対応) | 到達目標2の達成を目標に、栄養補給法の概要、経口栄養の特徴について学修する。
事前学習:該当部分の教科書を通読し、赤字の用語の意味を調べておく(30分) 事後学習:学習内容の復習及び形態別献立の特徴をまとめる(60分) |
| 4回 | 栄養・食事療法、栄養補給法2「経腸・静脈栄養補給法」(教科書:第1,2章に対応) | 到達目標2の達成を目標に、経腸栄養・静脈栄養の特徴について学修する。
事前学習:該当部分の教科書を通読し、赤字の用語の意味を調べておく(30分) 事後学習:学習内容の復習及び演習問題の解答(60分) |
| 5回 | 栄養・食事療法、栄養補給法3「経腸・静脈栄養補給法」(教科書:第1,2章に対応) | 到達目標2の達成を目標に、経腸栄養・静脈栄養の特徴について学修する。
事前学習:該当部分の教科書を通読し、赤字の用語の意味を調べておく(30分) 事後学習:学習内容の復習及び演習問題の解答(60分) |
| 6回 | 栄養アセスメント(特に食事調査)(教科書:第1章に対応)
★食事調査結果の返却 |
返却された食事調査結果をもとに、食事調査の概要について学修する。その後、食事調査分析結果をふまえて、プレゼンテーションを作成する。
事前学習:配布プリント内容の復習(30分) 事後学習:プレゼンテーション課題の作成を進める(60分) |
| 7回 | 老年症候群「サルコペニア、フレイル、低栄養」(教科書:第3章に対応)
|
到達目標2の達成を目標に、サルコペニア、フレイルの特徴と食事療法について学修する。サルコペニア患者の症例検討を行う。
事前学習:該当部分の教科書を通読し、赤字の用語の意味を調べておく(30分) 事後学習:学習内容の復習及び課題プリントの作成、演習問題の解答(60分) プレゼンテーション課題の作成を進める(60分) |
| 8回 | 栄養、代謝、内分泌系疾患1「肥満、メタボリックシンドローム」(教科書:第3,4章に対応)
|
到達目標2の達成を目標に、肥満の特徴と食事療法について学修する。肥満患者の症例検討を行う。
事前学習:該当部分の教科書を通読し、赤字の用語の意味を調べておく(30分) 事後学習:学習内容の復習及び課題プリントの作成、演習問題の解答(60分) プレゼンテーション課題の作成を進める(60分) |
| 9回 | 栄養スクリーニング、アセスメント
栄養ケアと実施 (教科書:第1章に対応) |
到達目標2の達成を目標に、SGA、MNA、体組成、血液・尿検査について学修する。症例を挙げて計算演習を行いながら栄養スクリーニング・アセスメント方法について学修する。
事前学習:課題プリントの用語を調べておく(30分) 事後学習:学習内容の復習及び復習問題の回答(60分) プレゼンテーション課題の作成を進める(60分) |
| 10回 | モニタリングと再評価
栄養スクリーニング、アセスメントのまとめ (教科書:第1章に対応) |
到達目標2の達成を目標に、臨床症状や栄養状態のモニタリングについて学修する。症例を挙げて計算演習を行いながら栄養スクリーニング・アセスメント方法について学修する。
事前学習:前回配布プリントの復習(30分) 事後学習:学習内容の復習及び復習問題の回答(60分) プレゼンテーション課題の作成を進める(60分) |
| 11回 | ★栄養ケア・マネジメントの実際 | 特別養護老人ホームに勤務されている管理栄養士の先生をお招きし、栄養ケア・マネジメントの実際について理解を深める。
事前学習:前回配布プリントの復習(30分) 事後学習:学習内容をまとめる(60分) プレゼンテーション課題の作成を進める(60分) |
| 12回 | ★アクティブ・ラーニング課題(食事調査結果をふまえた栄養管理計画の作成)の相互発表 | 到達目標3の達成を目標に、少グループに分かれ、これまで作成してきたプレゼンテーション課題を発表する。発表には、タブレット端末を用いる。プレゼン評価のルーブリックシートを用いて相互評価を行う。
事前学習:プレゼンテーションの練習(120分) 事後学習:評価シートをふまえて、プレゼンテーションの修正を行う(60分) |
| 13回 | 栄養、代謝、内分泌系疾患2「糖尿病」(教科書:第3,4章に対応)
|
到達目標2の達成を目標に、糖尿病の特徴と食事療法について学修する。
事前学習:該当部分の教科書を通読し、赤字の用語の意味を調べておく(60分) 事後学習:学習内容の復習及び課題プリントの作成、演習問題の解答(60分) |
| 14回 | 栄養、代謝、内分泌系疾患3「糖尿病(教科書:第3,4章に対応)
学修内容のまとめ |
到達目標2の達成を目標に、糖尿病の特徴と食事療法について学修する。糖尿病患者の症例検討を行う。
事前学習:前回配布プリントの復習(30分) 事後学習:定期テストに向けてこれまでの学習内容の復習を行う(180分) |
| 15回 | 定期試験 | 筆記試験 |
| 16回 | まとめ
定期試験の解説・授業の振り返り 授業評価の実施 |
定期試験の解説とこれまでの授業の振り返りを行い、最終的な到達目標1~3の達成度を確認する。
事前学習:定期テストで出題された部分について教科書、配布プリントを確認し、解答を予想しておく(60分) 事後学習:定期テストで出題された部分及び追加問題の学習(60分) |
| 成績評価の方法・基準 | 定期試験:70%
プレゼンテーション課題:20% ミニレポート、授業への積極的な参加:10% 上記を目安に、出席状況等を含め総合的に評価する。 |
|---|---|
| 教科書・参考書 | 教科書
「臨床栄養学実習書 第13版」¥2900(+税) ※2年次前期開講科目「臨床栄養学各論」「臨床栄養学実習」においても使用する。 参考文献 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」厚生労働省 |
| 履修条件 | 履修条件はなし。
ただし、学習内容が相互に関連することから、 2年次に臨床栄養学各論と臨床栄養学実習を合わせて履修することが望ましい。 |