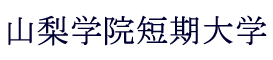子どもの食と栄養
青木慎悟・関戸元恵
2単位
保育科
| 履修系統図番号 | 8C-2058 |
|---|---|
| 科目区分 | 専門教育科目 |
| 必修、選択の別 | 選択 保育士必修 |
| 授業形態 | 演習 |
| 到達目標 | この授業が終了したときに、受講者の皆さんが次のような知識、技能を身につけることを到達目標とします。
1.健康な生活の基本としての食生活の意義や栄養に関する基本的内容について説明することができる。 2.子どもの発育・発達と食生活の関連について説明することができる。 3.食育の基本とその内容及び食育のための環境、地域社会・文化との関わりについて説明することができる。 4.家庭や児童福祉施設における食生活の現状と課題について説明することができる。 5.特別な配慮(食物アレルギーの対応等)を要するこどもの食と栄養について説明することができる。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業概要 | 本演習は、保育士資格取得の必修科目であり、「保育の対象の理解に関する科目」に位置づけられている。本演習では、子どもの心身の状態や発達過程の学習を踏まえた上で、子ども一人一人及び集団全体の食事と栄養について理解することにより、保育現場において子どもの食にかかわるための知識の習得をめざす。また、子どもや家庭への栄養指導、食育の重要性について、保育実践の場において活用できる力を養う。具体的には、子どもの健康と食生活の意義、栄養に関する基本的知識、発育・発達と食生活、食育の基本と内容、家庭や児童福祉施設における食事と栄養、特別な配慮を要する子どもの食と栄養について学習する。
※本授業は、状況によって、オンライン教材等を用いた遠隔授業を行います。 |
||||
| 学習内容 | ||
|---|---|---|
| 回数 | 内容 | 学習のポイント(事前事後の学習を含む) |
| 1回 | ガイダンス
子どもの健康と食生活の意義 (教科書:第1章に対応) |
この授業の到達目標1~5について確認する。
到達目標1の達成を目標に、子どもの健康と食生活の意義、子どもの食をとり巻く問題点について学習する。 事前学習:現代の子どもをとりまく食生活上の問題点を調べる(30分) 事後学習:食生活上の問題点をどのように改善したらいいか考えをまとめる(60分) |
| 2回 | 栄養に関する基礎知識
(教科書:第2章に対応) |
到達目標1の達成を目標に、栄養の基本的概念と栄養素の種類について学習する。
事前学習:5大栄養素を調べておく(30分) 事後学習:たんぱく質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラルの働きをまとめる(60分) |
| 3回 | 栄養に関する制度
(教科書:第3章に対応) |
到達目標1の達成を目標に、日本人の食事摂取基準と献立作成及び食事バランスガイドについて学習する。
事前学習:食事バランスガイドについて調べる(30分) 事後学習:食事バランスガイドを用い、自分の食生活の特徴・課題点をまとめる(60分) |
| 4回 | 妊娠期と授乳期の食生活
(教科書:第4章に対応) |
到達目標2の達成を目標に、乳児期の栄養法の種類と調乳方法について学習する。
事前学習:調乳の方法、衛生面、安全面での注意点を調べる(30分) 事後学習:母乳栄養の利点と問題点をまとめる(60分) |
| 5回 | 乳児期の食生活
(教科書:第5章に対応) |
到達目標2の達成を目標に、離乳食の意義と進め方について学習する。
事前学習:離乳食の必要性を調べる(30分) 事後学習:各月齢で食べられる食品と注意する食品、与え方のポイントについてまとめる(60分) |
| 6回 | 幼児期の発育・発達と食生活
(教科書:第6章に対応) |
到達目標2の達成を目標に、幼児期の心身の発達と食生活の意義について学習する。
事前学習:幼児期の食生活上の問題点を考える(30分) 事後学習:幼児期の食生活の課題をまとめる(60分) |
| 7回 | 学童期・思春期の発育・発達と食生活
(教科書:第7章に対応) |
到達目標2の達成を目標に、学童期・思春期の心身の発達と食生活の意義について学習する。
事前学習:学童期・思春期の食生活上の問題点を考える(30分) 事後学習:学童期・思春期の食生活の課題をまとめる(60分) |
| 8回 | 生涯発達と食生活
(教科書:第8章に対応) ★アクティブ・ラーニング課題(自身の食生活の特徴と課題)の相互発表 |
これまでの学習内容(妊娠期・授乳期・幼児期・学童期・思春期の発育・発達と食生活)の振り返りを行い、ライフステージを通じた食の重要性について学習する。
第3回で作成した課題について、小グループに分かれて相互発表を行う。 事前学習:第7回までの学習内容についてまとめる(30分) 事後学習:これまでの学習内容に対応した、保育士国家試験問題に回答し、正誤について調べておく(60分) |
| 9回 | 食育の基本と内容1
(教科書:第9章に対応) |
到達目標3の達成を目標に、食育の基本と食生活指導及び食を通した保護者への支援について学習する。
事前学習:食育基本法はどうして生まれたのか調べる(30分) 事後学習:食育基本法についてまとめる。(60分) |
| 10回 | 食育の基本と内容2
(教科書:第9章に対応) |
到達目標3の達成を目標に、食育を通じた家庭や地域への支援について学習する。
事前学習:「めざす子ども像」を調べる(30分) 事後学習:具体的な食育活動を立案し、指導計画の形でまとめる(120分) |
| 11回 | 家庭や児童福祉施設における食事と栄養
(教科書:第10章に対応) |
到達目標4の達成を目標に、家庭及び児童福祉施設における食事の現状と問題点について学習する。
事前学習:乳児院、養護施設における食事の問題点を調べる(30分) 事後学習:乳児院、養護施設における食事の問題点をまとめる(60分) |
| 12回 | 特別な配慮を要する子どもの食と栄養1
(教科書:第11章に対応) |
到達目標5の達成を目標に、疾病及び体調不良の子どもへの対応と問題点について学習する。
事前学習:疾病時の食事の内容はどのようにしたらよいかを調べる(30分) 事後学習:具合が悪い子どもにどのような対応をするか症状別にまとめる(60分) |
| 13回 | 特別な配慮を要する子どもの食と栄養2
(教科書:第11章に対応) |
到達目標5の達成を目標に、特別な配慮を要する子どもの食と栄養について学習する。
これまでの学習内容を振り返りながら、現時点での到達目標1~5の達成度を確認する。 事前学習:どのような障害の子どもにどのような支援をするか調べる(30分) 事後学習:これまでの学習内容に対応した、保育士国家試験問題に回答し、正誤について調べておく。定期試験に向けた学習を行う(120分) |
| 14回 | アレルギー疾患をもつ子どもの食と栄養
(教科書:第12章に対応) |
到達目標5の達成を目標に、食物アレルギーのガイドライン、食事提供の際のポイントについて学習する。
事前学習:保育所・幼稚園における食物アレルギー食品を調べる(30分) 事後学習:食物アレルギーに関する課題プリントをまとめる(60分) 事後学習:これまでの学習内容に対応した、保育士国家試験問題に回答し、正誤について調べておく。定期試験に向けた学習を行う(120分) |
| 15回 | 定期試験 | |
| 16回 | まとめ
定期試験の解説・授業の振り返り 授業評価の実施 ★アクティブ・ラーニング課題(食育活動計画に関する課題)の相互発表 |
定期試験の解説とこれまでの授業の振り返りを行い、最終的な到達目標1~5の達成度を確認する。
第10回で作成した課題について、小グループに分かれて相互発表を行う。 事前学習:これまでの授業内容を教科書・プリントで復習しておく(30分) 事後学習:授業内容を整理してまとめる(60分) |
| 成績評価の方法・基準 | 筆記試験(70%)、ミニレポート等の提出物(30%)
上記を目安に、出席状況等を含め総合的に評価する。 |
|---|---|
| 教科書・参考書 | 教科書
「子どもの食と栄養(第3版)保育現場で活かせる食の基本」(羊土社 ¥2,400+税) 参考資料 「保育所におけるアレルギー対応のガイドライン」(厚生労働省) 「保育所における食事の提供ガイドライン」(厚生労働省) 「乳幼児栄養調査」(厚生労働省) 「授乳・離乳の支援ガイド」(厚生労働省) |
| 履修条件 | なし |